
いつもご覧頂き本当にありがとうございます。
管理人の「はかせ」と申します。
今回の記事は自分が病気やケガをした時に
医者に書いて貰う「診断書」をテーマにして
我が子がいじめに遭った時
「診断書」を使って解決に導く方法
についてまとめて行きたいと思います。
我が子が実際にいじめの被害に遭うと、
暴力などのケガや悪口などで
心の病にかかってしまう事が多いです。
暴力のケガであれば
「実際に目に見える形」で残るので、
「いじめ」と「ケガ」の関係性(因果関係)を
診断書を使って証明する事は
比較的スムーズにできると思います。
問題は悪口などの直接証明する事が
難しいいじめの場合で、
「心の傷」が目に見えることが無いので
「いじめ」の関係性を証明する事は
非常に難しくなります。
被害を受けた事を証明できなければ
学校に訴えても動かない場合もあり、
時間がドンドン過ぎて他の問題
(不登校、出席日数が足らないなど)も
併発してしまう恐れがあります。
今回の記事ではそんな現代のいじめ問題の
解決策の1つとして、
「診断書」にフォーカスを当てて
被害を証明する手立てについて
まとめて行きますので最後までご覧下さい。
※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して
感じた事や学んだ事をベースにまとめていて
記事形式にして紹介しています。
「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、
風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。
もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、
あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。
実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと
解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いていますので
是非1度読んでみてください。
※いじめ問題と過去の裁判や判例についてまとめた記事はコチラ!!
意外と知られていない「診断書」の中身について

診断書とは、皆さんが知っている様に
「医師」が診断した内容を
詳しくまとめた書類になります。
- 症状の名称
- 診断した医師の所見
- 症状を治す時の注意点
- 完治するまでの期間
など、その病気にかかった理由などが
詳しく書かれている書類になります。
しかし診断書は「病状」や「治療期間」や
「結果」について書いている書類であり、
仮にいじめの状況や内容をはじめ
「受けた被害」などを証明する事が
書いていたとしても
医師は詳しい状況を知らないので
「事実を証明する書面」として
認められない場合があります。
暴力などの被害であれば話は別ですが、
悪口などのいじめだと
心にダメージ(うつやPTSDなど)を
受けた事を証明する事は非常に難しく、
より詳細なデータを引き合いにして
事実確認をしなければなりません。
要は、「どんな」被害を受けて
「どんな」傷(心の傷)を負い、
今の現状(うつやPTSDなど)になった事を
証明しなければならないと言う事です。
診察した医師の「診断書」1枚だけでは
我が子が受けた心の傷を証明する事は
難しいと言えるでしょう。
なぜ、診断書だけでは「いじめの解決」が難しいのか!?

なぜ、診断書だけだと
「いじめの解決」が難しいのか!?
先ほどまとめた様に、
診断書は「症状」や「治療期間」をはじめ
「今この病気(ケガ)になっていて
治るまでこれくらい掛かります」
という証明するものだからです。
このいじめに遭っているから
この病気(ケガ)になりましたと
証明したいのであれば
もっと詳しい状況証拠がないと
「被害」と「診断書」は
線で繋がりません。
体のケガであれば話は別で、
比較的容易でしょう。
例えばいじめで「うつ」になった場合を
考えてみると、
どういう症状(パターン)で
「うつ」と診断されるのか
基準を定めたものがあり、
有名な基準で言えば
- 「国際疾病分類(ICDー10)」
- 「うつ病エピソード(DSMーⅣ、Ⅴ)」
があります。
今回は「ICDー10」、
様々な国から疾病や傷害、
死因などのデータをとって
世界保健機構が統計をまとめた
分類の内容を例に
「うつ」と判断される為の
要件をまとめてみました。
その要件は次の通りで、
- 集中力の減退
- 自己評価と自信の低下
- 罪責感と無価値間
- 将来に対する希望のない悲観的な見方
- 自傷あるいは自殺の観念や行為
- 睡眠障害
- 食欲不振
これらの要件を総合判断して、
「うつ」であるかを見極める事になります。
しかし、その原因が「いじめ」であると
証明する事は簡単ではありません。
例えばこれらの症状の成立要件が
次の様に判断されてしまえば...
- 集中力の減退⇒(親との関係が悪化したから)
- 自己評価と自信の低下⇒(幼少期の親の虐待による)
- 罪責感と無価値間⇒(幼少期の親の虐待による)
- 将来に対する希望のない悲観的な見方⇒(幼少期の親の虐待による)
- 自傷あるいは自殺の観念や行為⇒(幼少期の親の虐待による)
- 睡眠障害⇒(進学や将来に対する不安、ストレスによる)
- 食欲不振⇒(進学や将来に対する不安、ストレスによる)
我が子が「うつ」になった原因は
「親の躾」が原因だと
判断されてしまう危険性があります。
実際、学校はこの様に判断させるために
動く事もあるかも知れないので、
いじめの事実関係を集めて
証明する様にしなければ、
いじめがあったから
こういう症状になったと
認めて貰う事は難しいでしょう。
医師の診断書を「いじめの解決」に結びつけるには

いじめで受けた被害
(身体的なもの、精神的なものなど)を
診断書で表したとしても、
実際にいじめとの因果関係を認める事は
難しく対応が遅れる場合もあります。
あくまでも我が子が受けたいじめを
証明する事をベースに、
- 被害内容は何なのか
- 誰がやったのか
- いつからなのか
- どんな症状なのか(診断書はあくまでもこの部分)
- 「症状」と「いじめ」との関係(こうだったから、こうなった)
いじめの証拠を自分たちで集めて、
早めに専門家に相談すべきでしょう。
さらに、過去の判例を調べた時に
「診断書」を活用する上で
重要なポイントがあったので
まとめてみました。
診断書を書いた日

精神的な被害、例えばうつだったり
統合失調症などの症状は「目に見えない」ので
いつからその被害を受けていたのか
分かりづらくて解決までに
時間が掛かってしまう大きな要因
でもあります。
精神的な被害を医師に早めに訴えていた場合
(診断にも時間が掛かってしまいますが)
診断書が書かれた日付と
「いじめを受けた日」が
密接に関連していれば
「いじめがあったからその被害を受けた」と
証明する事が出来るかも知れません。
先ほど参考文献で紹介した判例では
- 被害生徒がいじめを受けていた期間は中学校2年生の終わりから中学校3年生の2学期である
- 被害生徒が中学校3年生の2学期に不登校になった時には「うつ」になっていた
- いじめがエスカレートした中学校3年生の1学期に「うつ」に掛かっていたとは言えない
- 中学校3年生の2学期になってから学校の対応が不登校を改善する様に動いていた事(2学期からの学校の対応について安全配慮義務は認められない)
と判断され、中学校3年生の
1学期までのいじめについては
安全配慮義務違反を認めるけれど
2学期からの学校の対応については
安全配慮義務違反は認められない
(自殺とうつとの因果関係も認められない)と
判断されてしまいました。
もし中学校3年生の1学期の時点で
診断書で「うつ」と判断されていた場合には
「被害」と「うつ」との因果関係が認められて
「自殺」との関係性についても
違った判決がされた可能性が
非常に高いでしょう。
療養に必要な期間はどれ位なのか

診断書を書いてもらう時には
「療養に必要な期間」についても
書かれる事があります。
この療養に必要な期間は
症状によって変わってきますが、
この期間は病欠扱いとなり
「欠席」とされる場合がほとんどでしょう。
もし、いじめの事実関係が証明され
「ケガ」や「精神的な被害」との関係性が
認められる場合には、
長期欠席が被害の深刻さを表す事になり
「重大事態」として認識される可能性が
高くなります。
問題が重大事態と認識されるようになる為には
明確な指標はありませんが、
日数的には「不登校」の定義を当てはめ
「約30日前後」受けた被害が原因で
学校を欠席してしまうと重大事態
に該当する可能性が出てきます。
※「いじめの重大事態」について詳しくまとめた記事を載せていますので、一度読んで見てください。
「重大事態」と認識されると、
- 保護者に対する情報提供
- 「第三者機関」の設置
など学校が積極的に
介入してくれる様になります。
「いじめ防止対策推進法」では
「重大事態」についてこう書かれています。
第五章 重大事態への対処
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
出典元:文部科学省 いじめ防止対策推進法
さらに学校を長期で休んでしまうと
その分勉強が遅れる危険があります。
特に中学生であれば高校進学の内申に
影響してしまう可能性や、
高校生であれば欠席がそのまま単位修得に
影響してしまうでしょう。
そこで文部科学省では
「学校に行きたくても行けない生徒」の為に
出席認定の要件について公表しています。
学校に行けなくても被害の内容や
回復までの期間を診断書で
関係性を表す事が出来れば、
我が子の学習機会を確保する事が
出来るかもしれません。
私たち家族の時も学校との話し合いで
家での学習状況と学校に来れる時に別室で
補習を受けたりしながら
出席認定を貰う事が出来たので
学校に相談すると良いでしょう。
診断書を「頼むだけ」ではダメ!いじめの解決に役立てる方法について まとめ
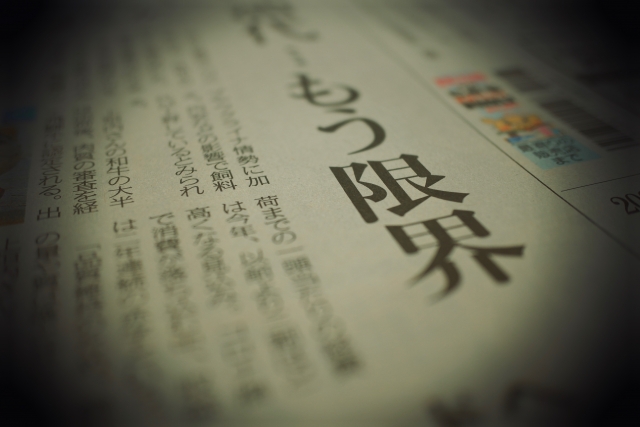
今回の記事は自分が病気やケガをした時に
医者に書いて貰う「診断書」をテーマにして、
『我が子がいじめに遭った時、
「診断書」を使って解決に導く方法』
についてまとめてきました。
診断書で勘違いをしてしまう事の
一番多い理由として、
「診断書があれば証拠は取れた」と
思ってしまう事です。
診断書はあくまでも医師の専門的な知識を元に
診察してみた結果を表しているだけなので
証拠以前の問題になります。
必要なのは「診断書に書かれた症状」と
「被害の内容」に関係性が
認められるのかであり、
診断書1枚で問題を解決出来る場合は
ほんのわずかでしょう。
あくまでもいじめは事実関係を
明確にする事が不可欠で、
受けた被害に対しては自分自身で
証明していかなければなりません。
また、事実関係を明確に出来たからと言って
「いじめ」が解決するわけではありません。
被害を受けて学校に行けなくなったり、
うつなどの精神疾患にかかる事も
あるでしょう。
そんな時に備えて、
診断書の所見を元に
「学校に行けない時の対処法」についても
併せて相談していく事が必要です。
今回の記事では「文部科学省」が
公表しているガイドラインを紹介しつつ、
出席認定を受けるための具体的な内容
(認定を受けた事例)も紹介していますので
一度読んでみてください。
もし、今現在いじめを受けて
誰にも相談できずに
1人で抱え込んでいるのなら
「いじめ-ラボ」に一度お話を
聞かせてもらえませんか!?
我が子が不登校になった時の話や
そこから学校へ復帰した経緯など、
記事には書いていない事も
話をさせてもらっています。
私たちが経験した内容が
少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。
いじめの対処法 「分からない」「どうすれば」をメールで受付中!

この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。
さらにこの記事を読んでいる
あなたをはじめ、
今現在いじめで悩んでいる方々に
少しでもお役に立てれる様に
日々勉強をしています。
そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、
分からない事などについて、
私たち家族が経験した事を中心に
『「いじめ-ラボ」の相談コーナー』で
随時相談を受け付けております。
- 我が子にいじめが発覚して、これからどうして良いのか分からない
- 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...
- 子供の様子がいつもとおかしい
- 誰にも相談出来なくて、今の気持ちを聞いて欲しい!
など、具体的な内容について
相談を受け付けていますので、
私たち家族の経験が
少しでもお役に立てたら嬉しいです。
※「いじめ問題」について具体的な質問やお問い合わせを受付中!
長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。


コメント