
いつもご覧頂き本当にありがとうございます。
管理人の「はかせ」と申します。
この記事では「いじめ 裁判」をキーワードに
「実際にあったいじめ裁判」を紹介してます。
なぜ実際にあった裁判の内容や
判決をまとめる必要があるのかと言うと、
いじめを裁判で争うときに
- 「いじめ」の何が問題になっているのか
- 事実の証明で「認められたもの」と「認められなかったもの」の違いは何か
- 「学校の対応」で問題となっているものは何か
- 実際にどれ位の期間が掛かるのか(事件の日と判決の日が書かれているから)
など、いろいろな情報を
(私たちがなかなか知り得ない事)
知る事が出来ます。
いざ裁判をやろうと考えても
実際には大勢の人と時間と
お金が掛かってしまうのは、
これを読んでいるあなたも
知っている通りだと思います。
さらに裁判で必要な証拠は
自ら集めなければならないので、
証拠として認められる内容は
どういったものなのかも
予め知る事も出来るでしょう。
判例は、今後このような痛ましい事件を
起こさないようにする為の教訓という
意味合いの他に、
加害生徒側や学校の対応について
責任を問う為の方法や経緯についても
書かれています。
本当に「いじめで自殺する生徒を減らす」と
考えているのであれば、
単に痛ましい事件がありましたと
過去形にするだけで無く、
・「事なかれ主義」の今の学校で、加害生徒や学校への責任を問う為にはどうすれば良いのか
私たち自身が判例を見て
考えて行くべきだと私は考えています。
「法律は知っている者のみを助け、
知らないままの者には
手を差し伸べる事は無い」
弁護士だけに任せっきりでは無く、
我が子の事は私たち親がしっかりと
守って行かなければならないと思います。
今回紹介するいじめ裁判事例は
平成20年にさいたま地裁で
行われたいじめ裁判事例で、
内容は小学校で起きた
いじめ問題の裁判です。
この裁判で争われた内容を、
- いじめの内容
- 学校の対応
- 裁判で判断された内容
に分けて紹介していきます。
また、題名にあるように
「いじめによる不登校と家庭環境の悪化」が
裁判の結果にどのような影響を
与えているのか調べつつ、
・我が子が学校に復帰する為に親が子供に出来る事
について詳しくまとめていきたいと思います。
※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して
感じた事や学んだ事をベースに
まとめていて、
記事形式にして紹介しています。
「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、
風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。
もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、
あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。
実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと
解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いてますので1度読んでみてください。
※いじめ問題についてまとめたサイトはコチラ!!
『いじめ-ラボ』
実際に行われたいじめの内容

今回、さいたまの小学校で起きた
いじめの内容をまとめていきます。
今回の被害者である生徒は
小学校5年生から6年生に
継続的ないじめを受けていました。
今回の裁判で明らかになった内容は、
【いじめの内容】
- 叩く
- 靴を盗まれる・隠す
- 消しゴムを切られる
- 鉛筆で背中を刺される
- トイレに閉じ込められる
- お金の問題(ねだられる)
- 筆記用具をなげる
※上記7つの項目がいじめについて
保護者同士が話し合いをし
和解をする前に起きたいじめ
- 悪口
- 給食時間に廊下に出される(みんなで決めた規則)
給食時間にうるさくしてしまうと
廊下に出されてしまうという
みんなで決めたルール
※上記2つの項目がいじめについて
保護者同士の話し合いの後に
起きたいじめとされるもの
といった、「仲間外れ」をベースとした
暴力や金銭のたかりが
目立った内容となっています。
※今回の事例の他に「小学校のいじめ(形態やいじめの発端など)について詳しくまとめた記事を載せていますので一度読んでみてください。
クラスにいじめがあったとされると
そのクラスが学級崩壊していた事が
裁判で明らかになる事はよくある事で、
今回の学校も学級崩壊があったのではと
裁判で争点になっています。
実際にはいじめが起きた時の
「クラス」の様子は
学級崩壊が起きるほどの状態ではなく
半数の男女が対立してはいましたが、
そんな中でも仲の良い男女がいて
仲良くしている風景も
たまにはあった様です。
今回の被害者である子も
仲の良い男子や女子の友達がいて、
後に不登校になった時でも
自宅まできて励ましてくれた事もありました。
お手紙のやり取りや電話とかで
被害者の子と話す機会は何度かあって、
よくあるいじめパターンの
「みんなから敵対視されている状態」
ではありません。
ただ、継続的に不登校になった状態で
- 学区内で行われるお祭りに参加
- 仲の良い友達とカラオケに行く
と「学校に行けない原因」が
クラスの友達にある訳では無い事が
徐々に裁判で明らかになり、
これからまとめて行く判例に
大きな影響を与える事になります。
では次に、問題点を「学校の対応」に
フォーカスを当てて見ていきましょう。
学校側の対応に問題はなかったのか!?

今回訴えられた小学校の対応に
問題は無かったのか!?
裁判で訴えられてしまった
学校側の対応を見ていきたいと思います。
まず始めに鉛筆で背中を刺したり
叩いたり等の「暴力」に関連する
内容について見ていくと、
- 被害者側の保護者との話し合いを踏まえて子供に対する対応を職員会議で話し合いをしている
- その話し合いの結果を他の先生にも周知徹底させている
この二つの事をしっかりと
学校側が行っている事が判明しています。
ただ、鉛筆を背中に刺した経緯を含めて
故意的に刺したのかどうかについて
判例に書かれていませんでした。
また、その他の「靴隠し」や
「給食やトイレでの問題」などの
「コミュニケーション系のいじめ」についても
- 子供達に個別に事情聴取をし、事実確認を徹底している事
- 特別扱いする事無く、みんなの問題としてクラスで対策に付いての話し合いをしている事
- 被害者の子と仲が良かった子が自宅まで行って話しをしたり電話で話ししたりと友達関係を維持する様に指導していた事
この3つの事が裁判で明らかになっています。
以上、上記5つの対応を
学校側が実施していた事が
裁判で「安全配慮義務」を
尽くしていたと判断され
「故意または過失」は認められない
と判断されました。
学校側には、生徒に対して
「安全配慮義務」を負っています。
簡単に言えば「いじめ」などの
問題が発覚した場合、
学校側にはその問題に対して
真摯に取り組み解決に向かってくという
義務があるというものです。
学校側が問題にしっかりと向き合い
対応する姿勢が見られない場合、
「安全配慮義務違反」となり
被害者側の損害を賠償する事になると
いうことになります。
例えば、
- いじめ問題について解決策などの話し合いに応じようとしない
- 子供同士の「じゃれ合い」と捉え、何もしない
- 大人の価値観でいじめを判断し、被害者からの訴えがあっても応じない
などの対応が学校側であれば、
「安全配慮義務違反」となる
可能性があると言う事になります。
以上、今回のさいたまの小学校で起きた
いじめ裁判の「学校側の対応」について
まとめていきました。
先ほども書きましたが
「学校側の責任」を追及していこうと
思っている場合には
「安全配慮義務」が
裁判の争点になります。
- 「いつ」から対応をしてくれているのか
- 「誰」が主体となって対応してくれているのか
- 「何」が問題なのか
- 「何故」対応しないのか
- 「どのような」対応をしているのか
※「何処で」は学校なので省いています。
よく言われる5W1Hをもとに
「学校側の対応」を形に残すなどの方法で
時系列にしてまとめると
裁判で明確に責任の所在を
追求する事が出来るでしょう。
裁判ではどんなジャッジを下したか!?
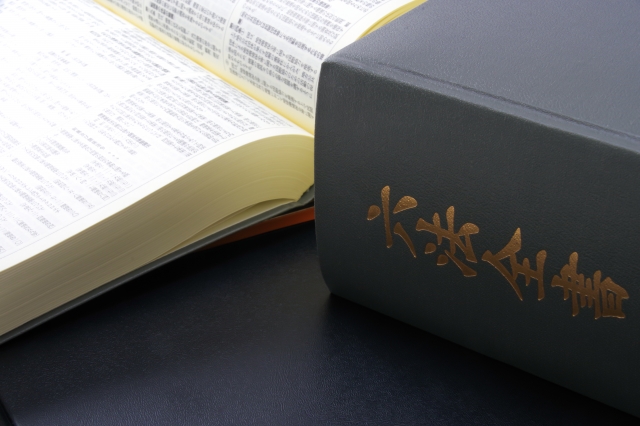
では、この段落では今回のいじめに対して
裁判所はどのような判断をしたのかを
まとめて行きたいと思います。
いじめられた子の保護者が
裁判で提示した請求内容は、
「被告ら(いじめっ子とその家族、学校)は原告(いじめられた側)に各自600万の賠償金を支払う事」
※いじめっ子は3人
(それぞれA、B、Cとする)と
その子達の両親(計6人)の合せて
9人と学校を相手に
各600万の損害賠償請求をしています。
前にまとめた「今回のいじめの内容」と
「学校側の対応」をもとに訴えた内容を
裁判ではどんな判断を
下したのでしょうか??
学校側の対応については、
先ほど説明したように
「故意や過失」は認められず
「安全配慮義務」は見られない
と裁判で判断されています。
では被害者側の請求や提示した証拠の内容は
裁判でどんな判断をしたのでしょうか?
裁判では被害者の学校での生活態度や
家での生活態度を次の様に判断しています。
- クラスでは特段問題が生じているわけでは無く、保護者同士の和解の後に行われたとされるいじめについても「心身の危険を感じさせる内容」ではない
- 被害者の子が不登校になった時に精神科の先生に「不安障害」と診断されているが、「いじめ」と「不安障害」との因果関係があいまい
- 和解した事と今回の裁判の間に「調停」を挟んでいるが、内容が調停を結ぶのに各自1000万を支払う内容で調停を申し込んで調停不成立となっている
- 精神科の先生に「診断書」を書いてもらう時に「不安障害」と診断される経緯が裁判で明らかになり、主に母親との関係や新しい父親との不仲が中心となっている
これらの事実を考慮して
被害者の子がいじめられ
「不安障害」と診断されて
不登校となった要因を、
「家庭環境」が影響の元となっている
と判断され、「被害者側の訴え」が
すべて棄却される事となりました。
不登校の原因が「家庭環境」にあると
判断された事について
一番影響を与えているものといえば、
不登校になっていた期間に
クラスの友達とお祭りやカラオケなど
遊びに行っていた事が大きいと思われます。
また、被害者側が証拠として提出した書類が
今回の問題が起きてから
相当な期間が過ぎた後に作成された内容で
事実があいまいであり、
請求金額が非常に高い内容となっていた事も
被害者側の証拠を否定された
要因の一つとなっているようです。
結果は保護者側の請求を全て棄却とする
(請求に理由が無い)判決となりました。
不登校が学校の対応だったり
いじめのせいだとして
「医師の診断書」を作成する方が
多いと思いますが
良くも悪くも子供は正直で
上手く誤魔化す事は出来ません。
今回の場合だといじめに遭った生徒の保護者は
再婚を予定していたらしく
中学校は別の所に進学する予定でしたが
上手く進まず子供に当たったり
新しい父親が暴れたりする事があったと
診断する時にこの生徒が話していた様です。
裁判ではこの時のカルテも
キチンと公開されていますので、
子供が本当は何に対して
恐怖を持っているのか
親としてしっかりと考えて
行かなければならないでしょう。
いじめによる不登校と家庭環境の悪化が裁判で争われた判例 まとめ

今回はさいたまで起きた
小学校いじめ事件を題材にして、
被害者側の請求を否定した判例を
紹介してきました。
実際にどんないじめがされてきたのかを
始めに紹介し、
そこから学校側の対応を詳しく見ていき
最後に裁判でどう判断されていったのかを
まとめてきました。
- 「学校側の対応」の内容
- 実際に「裁判」では学校の対応は妥当であると判断されている
- 被害者の子の不登校の原因は「いじめ」より「家庭環境」に重点が置かれている
- 結果的に被害者側の請求が不当
と、裁判で明らかになり
結果的に「学校側の対応」を問うよりも
「被害者側の家庭環境」に問題があるように
判断された結果となりました。
- 子供がどんないじめを受けて、どんな被害を受けたのか?
- 子供がこれからどうやって学校生活に復帰していくのか?
を中心に、「学校側の対応」や
「保護者同士の話し合い」を踏まえて
具体的な解決策を練っていく事が
いじめ問題の解決策の
王道パターンになると思います。
学校との話し合いや対応をしてもらう事は、
1回や2回話し合いをしただけでは
出来ません。
実際に私の子供がいじめられた時には、
学校に何十回と通って
こちら側の話を理解してくれるまで
話し合いを続けてきたました。
学校で起きたいじめは
何が原因で起きているのか、
対応は適正だったのかなど
しっかりと私たち親自身が
把握していかなければならないでしょう。
最後に「いじめ-ラボ」では
我が子のいじめをベースに
記事を更新しています。
その他の記事も随時更新してますので、
良かったら読んでみてください。
いじめの対処法 「分からない」「どうすれば」をメールで受付中!

この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。
さらにこの記事を読んでいる
あなたをはじめ、
今現在いじめで悩んでいる方々に
少しでもお役に立てれる様に
日々勉強をしています。
そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、
分からない事などについて、
私たち家族が経験した事を中心に
『「いじめ-ラボ」の相談コーナー』で
随時相談を受け付けております。
- 我が子にいじめが発覚して、これからどうして良いのか分からない
- 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...
- 子供の様子がいつもとおかしい
- 誰にも相談出来なくて、今の気持ちを聞いて欲しい!
など、具体的な内容について
相談を受け付けていますので、
私たち家族の経験が
少しでもお役に立てたら嬉しいです。
※「いじめ問題」について具体的な質問やお問い合わせを受付中!
長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。


コメント