
いつもご覧頂き本当にありがとうございます。
管理人の「はかせ」と申します。
私たち親の世代が子供の頃、
このサイトでテーマにしている
「いじめ」について
今くらいに問題になる事はあまり無く、
学校も保護者について神経質になったり
対応が雑になったりしてなかったと思います。
「9月1日問題」も
2000年辺りになってから
週刊誌で特集される様になりましたよね。
今回の記事のテーマにもなっている
「教師のいじめ」について
重なる部分もあるのですが、
今と昔でここまで対応に
変化が起きてしまったのは何故なのか?
これから書いていく記事は
千葉県で起きた小学校の教師による
わいせつ事件についてまとめたものです。
ある女子生徒2人(小学校時代)に対して
胸を触る等をし精神的苦痛を与え、
後に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を
発症させたとした事件として
特集していきたいと思います。
さらにこの2人の児童は少しだけ
ハンディキャップを負っている
生徒だった事が判明していて、
わいせつ行為をした教師に対する批判が
大きかったようです。
この事件を「浦安事件」として
ご存知の方もいらっしゃると思います。
この判例を調べて行きながら、
判決でどのように判断されたのか、
学校の対応に問題が無かったのかを
個人的な見解になってしまいますが
まとめて行きたいと思います。
※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して
感じた事や学んだ事をベースにまとめていて
記事形式にして紹介しています。
「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、
風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。
もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、
あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。
実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと
解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いていますので
是非1度読んでみてください。
※いじめ問題と過去の裁判や判例についてまとめた記事はコチラ!!
今回の事件の内容 教師が女子生徒2人に行った事

今回の事件において教師が
女子生徒2人にやった事について
調べて行きたいと思います。
被害当時、小学校の養護学級に通ってた2人に
担任だった教師が
胸を触る等のわいせつ行為等をしたと
被害に遭った生徒の1人から報告を受け
事件が明らかになったようです。
教室の隅の方に追い込まれて
日常的にわいせつ行為を受けていたと
被害生徒は主張し、
後に刑事裁判と民事裁判の両方を
起こす事となりました。
後の裁判で刑事裁判は
教師のわいせつ行為について「無罪」、
民事裁判は被害者側の意見を一部認め
教師と浦安市に対する損害賠償請求が
認められる形となりました。
学校の対応はどんな対応だったのか!?

当時のわいせつ行為を受けて
学校の対応はどうだったのかを
過去の文献を元に
まとめて行きたいと思います。
この教師が通っていた学校は
障害を持っている子に対して
個別に出来るレベルに応じて
指導を行っていく新設の学校で、
他の養護学校などのモデルスクールに
なっていた事が判明しています。
事件発生当初、教師は
「事実無根」と全面的に否定。
学校ではこの事件の前から
保護者とこの教師の間で
「指導不足」についてクレームが続いていて、
学級懇談会を開催し対応をしていた事が
判明しています。
対応していたのにも関わらず
再度問題が発生していた為、
何度も学校との話し合いが
持たれていたようです。
被害女子生徒の1人の両親が被害を訴えた時は
この教師について調査をしたのですが、
目撃証言が無い事や
教師が全面的に否定している為、
キチンとした事件の調査を行わないまま
「事件は無かった事」として
その後の調査を終了してしまいます。
事件が無かった事とされたので、
保護者が学校に要望していた心のケアや
対策もそのまま実行しないで放置。
後の裁判でもこの姿勢を崩す事は
なかったとしています。
今回の浦安事件を裁判ではどう判断したのか!?
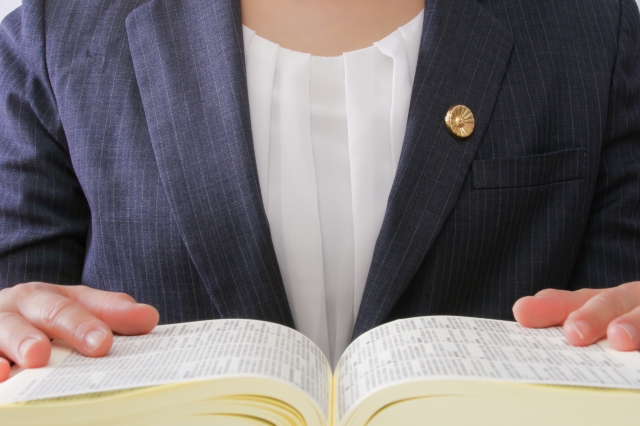
今回の事件で被害者家族は
「刑事裁判」と「民事裁判」の両方を
提起しています。
結論から書くと先ほど述べた通り
- 刑事裁判では「無罪」
- 民事裁判では被害者家族の請求を一部認め浦安市と教師に損害賠償をする
以上の判決を下します。
刑事裁判では罪を行った者の行為について
「有罪か無罪か」を決めるもので、
民事裁判では被害者が受けた損害を
どれ位の金額で加害者側が償うのかが
決められます。
この判決から言うと教師が行った
女子生徒へのわいせつ行為は「無罪」とされ
女子生徒が受けた損害は
一部支払う判決だと言えます。
無罪となったのなら、
慰謝料は払わなくて良いのではないか!?
と思われる方がいると思いますが
こういったケースはあるようで、
これから裁判を起こすと考えている方は
弁護士の方にキチンと相談すると良いです。
刑事裁判で「無罪」となったポイント

この裁判の判決を調べて行くと、
- 被害の状況がキチンと立証出来ない事
- 目撃者がいない
- 被害生徒の証言が曖昧になってしまった事
以上の事が判明し、教師が行った犯罪が
無罪とされてしまったようです。
特に今回の裁判では
被害女子生徒が知的障害が認められた事から
上手く話す事が出来なかったと思われます。
個人的な意見を言うと、
わいせつ行為自体キチンと内容を話せる事自体
稀なケースと思いますので、
事件の内容とわいせつ行為が相手に与える
精神的損害について
もっと歩み寄っていれば
生徒に負担を掛ける事無く
終わらせる事が出来たのではと思います。
私自身も我が子の裁判を通して
「証言や証拠の重要性」を
身に染みて感じていますが、
流石に小学生の子が証言する事について
精神的な負担は計り知れないものが
あったと思われます。
裁判は公平に行わなければ行けない事は
分かってはいるのですが、
親として側に居たらと思うと
苦しくなりますね。
民事裁判で一部認められたポイント

刑事裁判で無罪が確定してしまったのですが、
民事裁判では刑事裁判で
認められなかった被害について
認められる方向に動いています。
- わいせつ行為について被害があったとされる数十件の内の一部のみ(その後の控訴によってさらに範囲が広がった)認められる
- 証言や目撃者が居なくとも、被害者の証言などをまとめると高確率で「行為があった」と判断出来る事
当初被害者側が請求した金額ではありませんが
刑事裁判で「無罪」とされた事に対して
「わいせつ行為」があったと認めてくれた事が
大きいと思います。
被害を受けた女子生徒が証言しても
認められなかった事を認めてくれたのですから
当時の判決では大きな影響があった様です。
判決を受けて千葉県が
障害者差別禁止条例を全国は初めて作成し、
少しでも暮らしやすい環境を整えるように
動き始めました。
判決が出てからでは遅いと思いますが、
何もやらないよりはマシと
考えて行くしか有りませんね。
実際に裁判を起こしてみて...
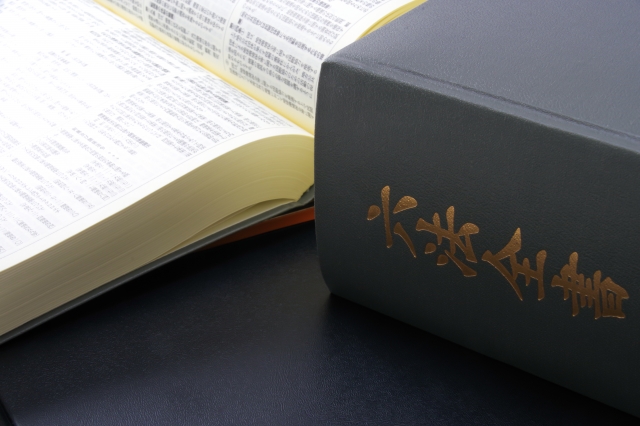
この強制わいせつ事件での
裁判もそうなのですが、
実際に問題が起きてから裁判が終わるまで
非常に長い期間が掛かります。
この事件で見れば問題が起きてから
裁判が終わるまで7年近くも掛かっている事が
調べてみて分かりました。
当時小学生だった女子生徒は
高校生位になっていて、
それまで心の傷を
背負っていかなければなりません。
女性ならではの被害ですので
私たち男が想像する以上に
精神的苦痛は大きかったと思います。
私「はかせ」も我が子のいじめで裁判を起こし
つい最近終わって(2018年)、
振り返って見ると
2年弱くらい掛かってしまいました。
今回の事件よりは早く終わる事が出来ましたが
終われば良い訳ではなく、
これから学校と教師が
この事件をどのように考えていているのか、
具体的な対策を取られなければ
本当に解決ではないという事です。
先ほども書いた通りに千葉県では全国で初の
「障害者差別禁止条例」を作りましたが、
これに限らず事実を深く受け止めてもらう様に
動かなければいけないと思います。
裁判だけで終わりではなく、
むしろそこから我が子との向き合いが
スタートするように思います。
今回の様な「性的被害」については
フラッシュバックする確率も高く、
内容が誰にも相談出来る内容ではないため
1人で抱え込む様になりがちです。
私が住んでいる宮城県では、
ある市で「いじめ対策」について
予算を大幅に増加させた市もありますし、
東京の方では「スクールローヤー」
学校内弁護士として働いている方も
いらっしゃいます。
全国でも珍しく教鞭を持ちながら
執筆活動もなさっている方で、
法律についての解釈や学校の対応について
読みやすくまとめてあります。
また小学生から高校生の未成年に対する
心のケアについて
(特に小学生から中学生までが注意)
私たち自身がサポートするにあたって
重要な対策という事を
認識する必要があるでしょう。
それに伴い女性の被害に対する認識についても
(セクハラ、レイプ、パワハラなど)
勉強して行く事が大事なのだと
我が子の裁判と今回の事例で学びました。
特に今回の事例でもとられた
「司法面談」について、
被害を訴える事が出来ない未成年について
どのように接して事実を
追いかけていけば良いのか
少しずつ親である私たちも
知る必要があるのではないでしょうか。
※「司法面談」とは??
今回の例のように物事の判断が付かない未成年に被害があった場合、ショックの方が強く当時の状況など正確な証言が難しい時の為の制度。
また未成年の記憶は周りの言動や雰囲気に惑わされやすく正確な証言でも誘導されてしまう危険性がある等、さらなる人権被害から子供の人権を守るための制度でもある。
もともと外国で行われている制度で、日本でも2010年以降から活動が活発になってきている。
参照文献:厚生労働省 第13章 特別な視点が必要な事例への対応
教師によるいじめや児童に対する性的虐待裁判「浦安事件」について まとめ

今回の記事は千葉県浦安市で起きた
「浦安事件」についてまとめた記事でした。
ハンディキャップを持っている女子が
教師にわいせつ行為を受けたとして、
被害者側が裁判を起こしますが
刑事では無罪で、民事では一部の行為について
損害賠償請求を認めた判決となっています。
今回刑事で認められなかったポイントと
民事で認められたポイントをまとめています。
大まかにまとめると、
- 被害者に証拠をまとめる事が出来なかった
- 目撃者がいない事
- 被害の性質から中々言えるものでは無い事
以上3つの原因で被告(教師)を
無罪としてしまいます。
しかし民事裁判では一転し、
「わいせつ行為」の一部を認め
損害賠償請求を認める判決となり、
判決を受けて千葉県では全国で初の
「障害者差別禁止条例」を制定します。
また、解決までには約7年ほど掛かっており
被害者の心のケアを考えると
これからの私たち大人の対策が
必要になる事は明らかになりました。
私たちの子供のいじめもそうなのですが
子供自身が身体に関するいじめをを
誰かに相談する事は
非常に難しいと言えるでしょう。
裁判では「証拠、立証」が不可欠なツールで
「子供の自発的な証言」が必要ですが、
それを子供に負わせる事には無理があります。
子供の人権を考える事も必要ですが、
私たち大人が現状を知り知識を付ける事も
必要になると私は考えています。
「いじめ-ラボ」では
我が子のいじめの被害をベースに
役立つ記事を更新して行きますので、
良かったら1度読んでみてくださいね!
もし、今現在いじめを受けて
誰にも相談できずに
1人で抱え込んでいるのなら
「いじめ-ラボ」に一度お話を
聞かせてもらえませんか!?
我が子が不登校になった時の話や
そこから学校へ復帰した経緯など、
記事には書いていない事も
話をさせてもらっています。
私たちが経験した内容が
少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。
いじめの対処法 「分からない」「どうすれば」をメールで受付中!

この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。
さらにこの記事を読んでいる
あなたをはじめ、
今現在いじめで悩んでいる方々に
少しでもお役に立てれる様に
日々勉強をしています。
そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、
分からない事などについて、
私たち家族が経験した事を中心に
『「いじめ-ラボ」の相談コーナー』で
随時相談を受け付けております。
- 我が子にいじめが発覚して、これからどうして良いのか分からない
- 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...
- 子供の様子がいつもとおかしい
- 誰にも相談出来なくて、今の気持ちを聞いて欲しい!
など、具体的な内容について
相談を受け付けていますので、
私たち家族の経験が
少しでもお役に立てたら嬉しいです。
※「いじめ問題」について具体的な質問やお問い合わせを受付中!
長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。



コメント