
いつもご覧頂き本当にありがとうございます。
管理人の「はかせ」と申します。
今回の記事は「いじめと大学」をテーマに、
大学で実際に起った事件を例に挙げて
まとめている記事になります。
その例となる事件は2007年に起きた
追手門学院大学で起きたいじめになります。
当時この大学に通う在日インド人大学生が
いじめを苦にマンションから飛び降り
自殺した内容になります。
普段からいじめがあり、
大勢の大学生がその内容を見ていた事から
事実確認の調査が行われたが
大学側は約3年近く問題を放置。
遺族側が弁護士会に「人権救済手続き」を
申し込む所まで発展した事件です。
この記事ではこの追手門学院大学の事件を
振り返って、
- いじめの内容
- 大学側の対応
- 法的観点からみて「大学のいじめ問題」の難しさ
- 大学に入学すると言うことについて
をまとめて行きたいと思います。
これから高校3年生は受験前の準備に
忙しくなると思います。
これからのビジョンを作って
(既に作っているかも知れませんが)、
夢と希望を持って
「不安」と戦っていきます。
せっかくの受験を制しても
夢や希望を持って入学しても、
大学でいじめは実際にあります。
しかも、生徒だけで無く
教授からのいじめも存在します。
この記事で「大学でのいじめ」の姿を
少しでも知って対策を取れるように
上手にまとめて行けたらと
思っております。
※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して
感じた事や学んだ事をベースにまとめていて
記事形式にして紹介しています。
「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、
風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。
もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、
あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。
実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと
解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いていますので
是非1度読んでみてください。
※いじめ問題と過去の裁判や判例についてまとめた記事はコチラ!!
追手門学院大学で起きたいじめ事件の内容
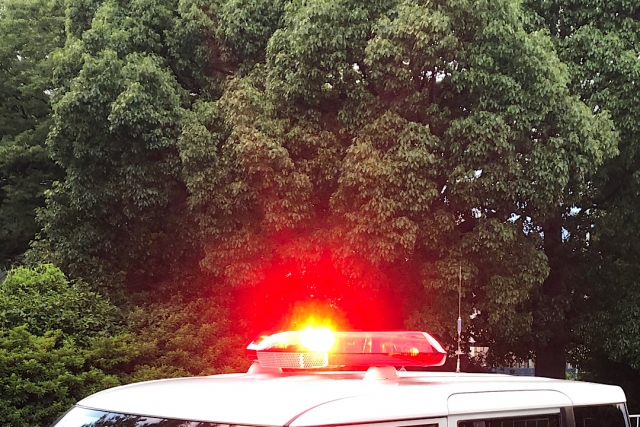
今回の記事のテーマにもなっている
「追手門学院大学で起きた事件」について
まとめて行きたいと思います。
当時この大学に通っていた在日インド人学生が
周りからいじめを受けており、
それを苦に自殺した事件。
そして後を追うように父親も同じマンションで
飛び降り自殺をした事で
当時ニュースになった事件でもあります。
自殺した学生が受けていた被害の内容は
- 某テロリストと容姿が似ている為にその名前で呼ばれてしまう事
- 大勢の人がいる所でズボンを脱がされる
と言った小学生並の内容となっています。
自殺した後にこの学生が書いた
遺書が発見されており、
その内容は、
- 「大学でいじめを受けていたこと」
- 「もう耐えられないから自殺をする」
といった事が書かれていました。
大学ではこの学生を養護してくれる
先生や仲間がいたのですが、
受けた被害が酷かったのか耐えられずに
自殺を選んでしまったようです。
この事から、ここで書いた内容以外にも
日常的に被害を受けていたのかも知れません。
当時この学生は家族と
一緒に暮らしていたことが
分かっていますが、
実際に自分がこのようないじめを受けて
家族に相談出来るのかと言えば
難しいと思われます。
事実、この学生の父親は
後追い自殺をしており、
我が子の苦しみを分かってあげられなかった事
守ってあげられなかった事が
理由とされています。
大学側の対応

この学生の自殺をうけて追手門学院大学は
どのように対応したのか??
大学側は学生の自殺といじめとの関係を
真っ向から否定。
大学と遺族との窓口的役割を果していた先生も
大学側の意向でこの事件から外され、
実質大学側が強制的に
遺族とのコンタクトをしない様に
仕向けた対応も見られました。
これらの対応を遺族側は
「弁護士」を要して対応を進めるも、
- 「小・中・高校のいじめとは違う」
- 「大学側の弁護士は対応しなくとも良いと判断した」
といった発言で、
一向に対応を進めませんでした。
さらには今回の事件の調査によって
他の関係者も迷惑が掛かっているから
調査はこれ以上出来ないとして行わなかったり
大学内の委員会でも調査を進めるように
話し合いを持たれても
調査が行われる事はありませんでした。
そして最後に自殺から3年後の
平成22年の2月に遺族との和解を前提とした
「見舞金」を遺族側に納める際に
お互いに権利主張をしない旨を合意する
書面にサインを求められた
として大阪弁護士会に
「人権救済手続きの申立て」を
申請する事となりました。
ここまで保守的・無関係になれる
大学の対応は類を見ない物でしょう。
学生が自殺した当時のメディアでは
「いじめ=自殺」の認識が
既に出来ている時期でもありますので
遺書まで出ていたのにも関わらず
対応をしなかった大学側の責任は
非常に重いものだったハズです。
では次に「大学側の責任」について、
若干私の考えも混じるかも知れませんが
まとめて行きたいと思います。
今回の「大学側の動き」にどう対応すれば良いのか!?

ここでは大学で起きた
いじめ問題の対応について詳しく調べて、
それに伴い、小中高の問題と
大学での違いについても
詳しくまとめて行きたいと思います。
今回の大学側の対応を振り返ると同時に、
まず始めに「いじめ防止対策推進法」を
ピックアップしていきます。
この法律ではいじめ問題全般について
- 問題の定義
- 国や地方公共団体の対応
- 学校の対応
- 保護者の対応
- 問題が深刻になった場合について
以上のポイントに分かれて
まとめられています。
この「学校」というフレーズについて
詳しく見ていくと、
この法律では「学校」を次の様に
定義していることが分かりました。
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
引用元:文部科学省
この「学校教育法」で定められている
小学校から高校までが
この法律の範囲内とされているので、
基本的に大学は範囲外と言うことになります。
なので今回の様な大学側の対応について
この法律では対応が難しい事になります。
ただ、在学中の安全配慮義務については
大学でも適用される様ですが
大学生になるとほとんど
20前後の年齢になっていますので、
- 安全配慮義務についての範囲
- どのくらいの配慮で足りるのか
- その対応の方法について
これら3つを比較して考えて見ると、
大学側の安全配慮義務については
小中高に比べると若干弱い様です。
(ただし、専門的な実験や活動については
小中高と比べると厳しくなる様です)
しかし、今回の追手門学院大学の事件の場合
いじめがどれほど酷い内容なのかを始め、
- ほかの学生がどれだけ知っていたのか
- 大学教員に対して相談はしていたのか
を調査して裁判で争う事は
もちろん可能だと思われます。
実際、隠蔽と思われる対応やウソの供述、
「権利放棄を要求する書面へのサイン」まで
行われているので
裁判では「安全配慮義務違反」に
問われる可能性は非常に高いと思われます。
また、最近では
「アカハラ(アカデミックハラスメント)」
と言ったように大学機関での
精神的な圧力について苦痛を受けた事について
訴訟を起こす動きも活発になってきています。
NPOアカデミック・ハラスメントをなくす
ネットワーク(NAAH)では
「アカハラ」を次の様に定義しています。
研究教育に関わる優位な力関係のもとで行われる理不尽な行為
引用元:NPOアカデミック・ハラスメントをなくすネットワーク(NAAH)より
今回の追手門学院大学のケースで見ていくと、
いじめ問題を意図的に
隠蔽しようとしていた事が判明すれば
「アカハラ」と認定する事は
可能だと思われます。
例えば、
- 被害者に対する不当な圧力
- いじめに関する供述をした場合には研究をさせない、ゼミを受けさせない
などと言った行為が認められれば
「アカハラ」で訴える事も出来るでしょう。
実際に「自殺した学生」と「大学側」との
窓口になっていた大学教員は
意図的にこの問題から
外されてしまっていますので、
「何らかの圧力」が掛かっているのであれば
この教員から問題の真意について
大学側へ問いただすことは可能でしょう。
大学に入学するという事について

前の段落まで
「追手門学院大学のいじめ」について
まとめてきました。
ここでは実際に「大学」という所に
入学する事についてまとめていきます。
この記事を書いている私自身は
高校卒業で学歴が終わっているので、
「大学」と聞くと非常に羨ましく思います。
当時はすぐに働きたいと思っていたので
大学進学は全然考えておらず、
実家が貧しかった事もありましたので
遠い存在にしか感じませんでした。
大学に進学する時、
大抵の希望者は地方から上京したり
他の地域に移動して
「1人暮らし」を始める人が多いと思います。
今までは家族がいたのに新しい生活を1人で
迎えなければない事になります。
最初の内は1人で気軽だと思いますが、
段々と1人が不安になってくるハズです。
そういった時に気軽に相談出来る人や
家族がいると精神的に頼もしいでしょう。
普段は無口の子供でも、
実際は心細い所を見せたくないから
何もしゃべらない事もあるでしょう。
多分、口に出したらいっぱい出てくるから。
一緒に居れる内に「笑顔」を沢山見せておいて
いつでも話せる関係を作る必要があります。
大学までもいじめを隠蔽 追手門学院いじめ事件の内容 まとめ

今回は2007年に起きた
「追手門学院大学のいじめ事件」について
まとめてきました。
当時この大学に通っていた在日インド人学生が
自殺してしまった事に対する
大学側の対応の杜撰さが
世間に広まった事件でもあります。
自殺した時に学生は遺書を残しており
自殺の原因も明らかなのにも関わらず、
大学側の対応は調査もしないし事実も認めず
最後には遺族側に
「権利を行使しない旨」の誓約書に
サインを求める事まで進める始末。
この大学の姿勢は弁護士を通しても変わらず
大阪弁護士会に「人権救済手続きの申立」を
起こすまでになりました。
今回の記事では、
「大学で起きた事件」と言う事で
問題が起きた時に出来る事も
併せてまとめてみました。
本来規定されている
「いじめ防止対策推進法」では
高校までしか対応していないので、
この法律で大学の責任を
追及する事は難しいでしょう。
その面を踏まえた上で、
大学と学生との関係に注目して
「安全配慮義務」や
「アカデミックハラスメント」についてにも
まとめています。
この問題が高校までの問題では無く、
大学ひいては社会に出ても
起こりうる問題なのだと
認識する事が大事なのだと私は思います。
1人1人が様々な考えや生き方を持っていて、
それぞれに価値がある事を尊重出来る様に
この事件を風化させないように
していきましょう。
そこで、このサイトでは
「いじめ発生から裁判を起こした経験」を元に
「相談コーナー」を実施しています。
もし、今現在いじめを受けて
誰にも相談できずに
1人で抱え込んでいるのなら
「いじめ-ラボ」に一度お話を
聞かせてもらえませんか!?
我が子が不登校になった時の話や
そこから学校へ復帰した経緯など、
記事には書いていない事も
話をさせてもらっています。
私たちが経験した内容が
少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。
いじめの対処法 「分からない」「どうすれば」をメールで受付中!

この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。
さらにこの記事を読んでいる
あなたをはじめ、
今現在いじめで悩んでいる方々に
少しでもお役に立てれる様に
日々勉強をしています。
そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、
分からない事などについて、
私たち家族が経験した事を中心に
『「いじめ-ラボ」の相談コーナー』で
随時相談を受け付けております。
- 我が子にいじめが発覚して、これからどうして良いのか分からない
- 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...
- 子供の様子がいつもとおかしい
- 誰にも相談出来なくて、今の気持ちを聞いて欲しい!
など、具体的な内容について
相談を受け付けていますので、
私たち家族の経験が
少しでもお役に立てたら嬉しいです。
※「いじめ問題」について具体的な質問やお問い合わせを受付中!
長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。


コメント