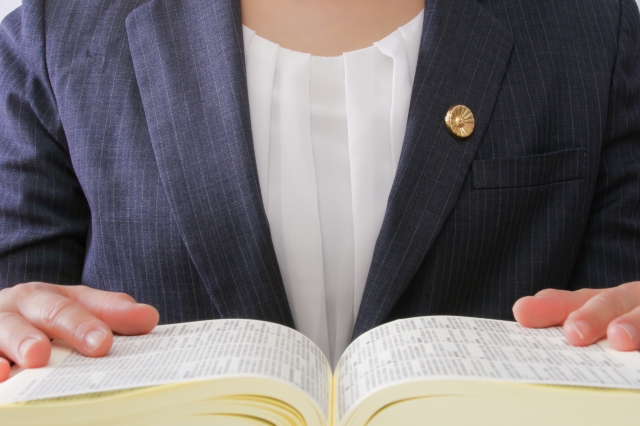
いつもご覧頂き本当にありがとうございます。
管理人の「はかせ」と申します。
この「いじめ-ラボ」では、
実際に我が子がいじめの被害に遭い
裁判を起こして解決するまでの
いきさつを基に記事をまとめています。
2018年に無事全て終わり、
我が子も学校生活を何とか過ごしています。
この記事を見てくれているあなたを始め、
私たち家族の経験が
今現在この問題に悩まされている方々へ
少しでもお役に立てればと
記事にまとめさせて頂いています。
この記事にも、関連するであろう
記事を紹介させて頂きますので
良かったら読んでみてください。
今回の記事は実際に裁判を
起こそうと考えている方や、
裁判まで行かなくとも弁護士の方に
相談する時によくある「気になる事」について
まとめて行きたいと思います。
私たち家族もいざ裁判をやるとなった時に
気になる事がありました。
多分あなたも同じのハズ...。
- 「子供のいじめでも相談受けてくれるのか」
- 「裁判自体、どのくらいの時間が掛かるのか」
- 「費用はどのくらい掛かるのか」
このポイントが
気になるポイントになると思います。
裁判になるとドラマでよくある風景が
そのまま現場で繰り広げられます。
ただ、いじめ裁判となると
「民事裁判」となりますので、
被告人とかはいませんし、
裁判官が目の前に数人並び
原告側の弁護士と被告側の弁護士が
向かいあって話し合いを始めます。
人数で言えば、規模によって変わりますが
私たちの場合だと裁判官が3人と弁護士2人、
何故か被告本人が弁護士を雇わずに
証言をしていました。
裁判では「原告、被告自身」が
弁護することも可能ですが、
全ての手続きを自分自身で行わなければならず
知識も自分でまかないながら
裁判を行わなければなりません。
自分で全て行うのであれば
当然費用の面を考えると格安になりますが、
不要な一言で事実を
「白」にも「黒」にもさせてしまいます。
もし、今回我が子の受けた体や心の傷を
裁判で証明するのであれば
この記事がお役に立てると思います。
※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して
感じた事や学んだ事をベースにまとめていて
記事形式にして紹介しています。
「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、
風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。
もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、
あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。
実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと
解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いていますので
是非1度読んでみてください。
※いじめ問題と過去の裁判や判例についてまとめた記事はコチラ!!
弁護士に相談!!実際に相談してみて思った事

冒頭でもお話したように、
私たち家族は2年位前に
いじめの裁判を起こし最近終わりました。
当時担当してくださった弁護士の先生には
今でも連絡を取り、
その後の対応についてもお任せしています。
その後の対応としては
被告から支払われた賠償金を
1度弁護士事務所へ入金してもらい、
後に私たちの口座へ
入金してもらう事が大半です。
後にご紹介しますが、
弁護士費用は「分割も可能」ですので、
分割している分を差し引いて
毎月入金をしています。
ホームページで「分割可能」と
書いている事務所もありますし、
書いて無くとも相談に乗ってくれる
事務所も有りますので
1度確認してみると良いですよ!
私たちの場合、弁護士の紹介は
「都道府県の弁護士会」からの紹介でした。
裁判を起こす前の
「和解・調停手続き」も行っていて、
その時の弁護士の紹介も
都道府県の弁護士会からしてもらいました。
依頼するための金額が大きい上に、
専門知識を必要とする資格ですから
一般的に「敷居が高い」イメージを
持っている方々が多いと思います。
どんな人が弁護士なのか!?

私たちの目の前に表れたのは、
一目見ただけで分かる
いかにも「弁護士」と言った
雰囲気を持っている男性でした。
「やっぱり取っつきにくい感じなのかな」
見た目ではそんな感じを受けたのですが
話をしてみると物腰落ち着いている
やんわりとした話しやすく、
特にいじめ問題をよく扱っている先生と
言う事もあり、
「被害者側の話」を最後まで聞いてくれて
要点を汲んでくれる先生でした。
全て話し終えると、
「後はコチラにお任せください。」
と二つ返事で依頼を受けてくださいました。
今、この時を振り返ってこの先生に頼んで
本当に良かったな思います。
弁護士会からの紹介の前に
独自に弁護士を探していたのですが
コチラの話を聞いた後で、
- 「法律上、相手方(加害者側)へ請求となると難しいかも知れません」
- 「(中には、加害者側の人数をしってから)和解で金額の妥当なラインを決めた方が良いですよ」
と、確率上「勝てない」と分かった裁判は
出来るだけ避ける様な弁護士もいました。
そんな中の今回の弁護士の方だったので、
凄く安心したのを覚えています。
今回の裁判で私たちの運が良かっただけ
なのかも知れませんが、
「いじめ」に対して法律論だけで無く
「正義感」で真摯に向き合ってくれる
弁護士の方もいらっしゃる事が分かりました。
「敷居が高い」
そう思っている方は多いかも知れませんが
無料相談などを通して
「自分のケースにあった弁護士」を
探してみる事が大事だと学びました。
弁護士に依頼した時にどれ位費用が掛かったのか!?

ここでは、実際に弁護士に依頼した時に
「費用」はどのくらい掛かったのかを
まとめて行きたいと思います。
弁護士の「費用」については
一概に「これだけ掛かる」と言った
明確なラインは無く、
その事務所ごと定めている報酬額があります。
なので私自身掛かった費用は
「別の記事」にてまとめますので、
これから「よく見られる費用の種類」について
書いていきます。
弁護士の費用については
様々な形態が存在していますので
一概には言えませんが
数十万からのスタートが一般的な様です。
調べて見ると、弁護士費用について
5つの費用が掛かることが判明しています。
- 着手金
- 成功報酬金
- 相談費用
- 事務手数料
- 調査などに掛かった費用
その他にもいろいろと掛かるようですが、
一般的に掛かる費用として
これら5つの項目が代表的な例でしょう。
1,着手金

「着手金」とは、
依頼をする時に払う費用の事です。
CMでよく流れているキーワード、
それが「着手金」です。
弁護士費用といって真っ先に思い当たる金額が
この「着手金」になります。
イメージ通り高い金額の所もあれば、
案件に応じて変動する所もあります。
また、「依頼をする時に払う」ものになりますので
依頼した案件が失敗した場合でも
返却は出来ません。
また、裁判前の「和解・調停手続き」
いわゆるADR(裁判外紛争解決手続き)にも
着手金が別途掛かりますので、
ADRの時の先生で引き続き
裁判の依頼をする場合は気を付けてください。
※ADRの費用は
大体20,000円になります
2,成功報酬金

これは「着手金」とは逆で、
依頼が成功した時に別途金額を払うものです。
この金額は必ずしも発生する訳でなく、
中には設定していない場合もあります。
この金額の算出方法は固定の金額では無く、
- 裁判で勝訴した時の損害賠償額につき「~%」の割合で弁護士に支払う方法
- 裁判の時に設定した金額に基づいて「~%」の割合で弁護士に支払う方法
のように個別に定められているようです。
3,相談費用

ある問題を弁護士に
相談するときの費用になります。
いろいろ調べてきたのですが、
この相談費用の相場はだいたい
「5,000~10,000円」
の間で推移しているようです。
よくある方式では「初回のみ相談無料」
という所もあります。
結構な所で「初回無料」と
設定している所が多いですので、
相談してみての感じで
「どこに相談するのか」を
決める事も出来ます。
また「相談する時間」で決めている所もあり、
開始~分は無料、その後30分につき
数千円徴収という所もあります。
4,事務手数料

この項目は「書面作成の費用」などが
メインになる費用です。
いわゆる内容証明で相手に通知する場合、
よくあるケースは不倫相手に
警告文を送る場合の書面や
借金の返済の催告などに
あてがわれる費用です。
中には着手金のなかに含まれている所も
あるようですので、
個別に弁護士事務所へ確認するといいですよ。
5,調査などに掛かった費用

この費用は依頼主が遠方にいる為に、
出向くときに掛かった
交通費などが該当します。
特に「いじめ問題」は隠蔽されたり、
学校の対応が杜撰だったりする場合など
「加害者側の素行」を調査する時に
発生する可能性があります。
遠方であればあるほど、
時間が掛かるものであればあるほど
「泊まりがけ」で
調査したりする事もありますので
その費用として徴収される場合があります。
以上、簡単に弁護士に掛かる費用を
まとめてみましたが、
ベースになる費用は予め弁護士協会の方で
取り決めがあります。
それに基づいて独自に選定するように
なっている様ですので、
ここで挙げた内容を
個別に確認すると良いでしょう。
弁護士に依頼する前にやっておきたい事

私たちが実際に裁判をやってみて
大体2年位掛かっています。
中には裁判で10年間近く
解決に掛かったものもあります。
「この月日の差」はいかに自分たちで
証拠を集めることが出来たのかに
直結する内容です。
裁判だけに関わらず、
その後の対応も必須になります。
裁判をしている時でも
我が子の学校生活を守るために
話し合いを継続しなければなりませんでしたし
裁判で話し合いがもつれればその度に
「その証拠を自分たちで立証」
していかねばなりません。
よく言われるのが
「弁護士に任せておけば後は大丈夫」
と言うこと。
実際にはそんなことは無くて、
「裁判に必要な証拠」は
弁護士でも集める事は出来ますが
我々自身も集めなければなりません。
実際に被害を受けているのは
私たちの子供なので、
その被害状況は弁護士よりも
「被害を受けた人間」が
一番よく分かっています。
弁護士に明確に「事実の全容」を伝える為にも
継続して学校との話し合いを基に
「証拠」を集めなければなりません。
例えば、「アンケート」なども
事実の全容を掴むためには必要不可欠です。
我が子が不登校になってしまった時にも
「どのくらいの日数休んでしまったのか」
予め把握しなければなりません。
これによって「いじめの深刻度」が
変わるからです。(重大事態)
これが明らかになる事によって
「学校の対応」も変わる時が実際にあります。
学校だけで無く「教育委員会」も
積極的にいじめを認めることもあります。
最初に私たち自身が証拠を集めることで、
その後の弁護士への流れが
スムーズになります。
それに伴って、
解決までの時間も短縮されるでしょう。
弁護士にお願いしたからと言って
終わりではなく、
依頼する前にある程度の証拠を
自ら集めておく事が必要です。
いじめを弁護士に相談する時の「気になる事」まとめて見た まとめ
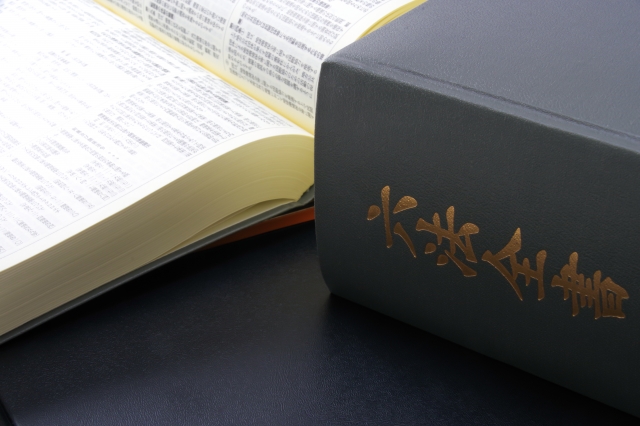
今回の記事は実際にいじめ問題で
弁護士に相談したときの
内容を基に作りました。
その時に「気なる3つのこと」について
まとめてきましたが、おさらいすると
- 「子供のいじめでも相談受けてくれるのか」
⇒「敷居が高い」と感じる人も多いですが、話をしてみると親近感をもつ弁護士の方もいらっしゃいます。 - 「裁判自体、どのくらいの時間が掛かるのか」
⇒私たちのケースは約2年。ケースごとによって、または自分たちの証拠が何処まで揃っているのかにもよる - 「費用はどのくらい掛かるのか」
⇒ケースごとに変化するけれど、基本的なのは記事にまとめてある通りです。
裁判には非常に時間の掛かる場合もありますが
私たち自身で証拠となる事実を
集めることが出来れば
時間を短縮する事も
可能な場合があります!!
裁判だけに囚われず、
「我が子の為に何が必要なのか」を
じっくり考える事が必要です。
もし、今現在いじめを受けて
誰にも相談できずに
1人で抱え込んでいるのなら
「いじめ-ラボ」に一度お話を
聞かせてもらえませんか!?
我が子が不登校になった時の話や
そこから学校へ復帰した経緯など、
記事には書いていない事も
話をさせてもらっています。
私たちが経験した内容が
少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。
いじめの対処法 「分からない」「どうすれば」をメールで受付中!

この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。
さらにこの記事を読んでいる
あなたをはじめ、
今現在いじめで悩んでいる方々に
少しでもお役に立てれる様に
日々勉強をしています。
そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、
分からない事などについて、
私たち家族が経験した事を中心に
『「いじめ-ラボ」の相談コーナー』で
随時相談を受け付けております。
- 我が子にいじめが発覚して、これからどうして良いのか分からない
- 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...
- 子供の様子がいつもとおかしい
- 誰にも相談出来なくて、今の気持ちを聞いて欲しい!
など、具体的な内容について
相談を受け付けていますので、
私たち家族の経験が
少しでもお役に立てたら嬉しいです。
※「いじめ問題」について具体的な質問やお問い合わせを受付中!
長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。
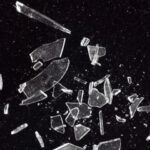

コメント