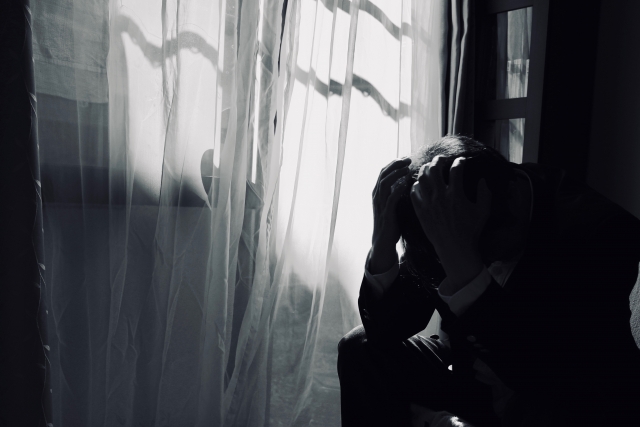
いつもご覧頂き本当にありがとうございます。
管理人の「はかせ」と申します。
今回まとめた記事は「いじめ 裁判」
というキーワードで、
「うつ」になった事を裁判で認めさせるには
どうすれば良いのかをまとめてみました。
なぜ実際にあった裁判の内容や判決を
まとめる必要があるのかと言うと、
いじめを裁判で争うときに
- 「いじめ」の何が問題になっているのか
- 事実の証明で「認められたもの」と「認められなかったもの」の違いは何か
- 「学校の対応」で問題となっているものは何か
- 実際にどれ位の期間が掛かるのか(事件の日と判決の日が書かれているから)
など、いろいろな情報を
知る事が出来るからです。
(私たちがなかなか知り得ない事)
いざ裁判をやろうと考えても
実際には大勢の人と時間と
お金が掛かってしまうのは、
これを読んでいるあなたも
知っている通りだと思います。
さらに裁判で必要な証拠は
自ら集めなければならないので、
証拠として認められる内容は
どういったものなのかも
予め知る事も出来るでしょう。
判例は、今後このような痛ましい事件を
起こさないようにする為の教訓という
意味合いの他に、
加害生徒側や学校の対応について
責任を問う為の方法や経緯についても
書かれています。
本当にいじめで自殺する生徒を減らすと
考えているのであれば、
単に痛ましい事件がありましたと
過去形にするだけで無く、
・「事なかれ主義」の今の学校で、加害生徒や学校への責任を問う為にはどうすれば良いのか
私たち自身が判例を見て考えて行くべきだと
私は考えています。
法律は知っている者のみを助け、
知らないままの者には手を差し伸べる事は無い
弁護士だけに任せっきりでは無く、
我が子の事は私たち親がしっかりと
守って行かなければならないと思います。
以上を踏まえて紹介する判例は、
平成11年に起きた
「栃木県の中学校いじめ自殺事件」です。
内容は、中学3年生である被害者生徒が
加害生徒から継続的にいじめを受け、
最後には自殺をしてしまいます。
そして遺族(両親)側は我が子が自殺したのは
学校側が対応してくれなかったからだとし、
学校側を相手取り
裁判を起こす事になった事例です。
この事件の裁判内容でのポイントは
題名にもあるように
「いじめ」と「うつ」との
関係性が争われた事例
という事で、
- 「うつ」になった事を相手側に認めさせる事は出来るのか!?
- また、「認めさせる」為には何が必要なのか
を裁判の内容を元に
書いていきたいと思います。
長文となりますので、
「目次」をクリックすると
各項目にジャンプします。
必要な内容から
見てもらって構いませんので
じっくり読んで頂けると嬉しいです!!
※この判例がでた時には
「いじめ防止対策推進法」は
まだ制定されておらず、
今回の内容が制定された法律を元に
進めて行くと違った結果に
なるかも知れません。
なので「起こりえる判決の一つ」として
見てください。
今回起こった事件を、
- 事件の内容はどんなだったのか
- 学校の対応はどうだったのか
- 裁判でどう判断されたのか
の3つに分けて、
今回の問題を詳しく
見ていきたいと思います。
※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して
感じた事や学んだ事をベースにまとめていて
記事形式にして紹介しています。
「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、
風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。
もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、
あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。
実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと
解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いていますので
是非1度読んでみてください。
※いじめ問題についてまとめたサイトはコチラ!!
『いじめ-ラボ』
今回のいじめ自殺事件の内容はどんなだったのか

今回行われた「いじめ」の内容を
箇条書きでまとめて見ました。
被害生徒を「A」とし、
加害者側を「B、C」とします。
調べて見ると、中学生のいじめと言うより
「奴隷」として被害者を常日頃から
クラスで扱っている事がうかがえる
内容となっており、
裁判でも「人格否定」をする卑劣な行為として
加害者側を批判しています。
※中学生にありがちな「いじめ」のパターンについて詳しくまとめた記事を載せていますので一度読んでみてください。
【内容】
- 常日頃から「肩パン」や「プロレスごっこ」と称して暴力を振るう
- Aのズボンを脱がし、女子生徒の面前で性器を見せびらかす
- Aの顔をサインペンでいたずら書きする
- Aの前髪を切られる
- 自転車の荷台やカゴを壊される
- 教科書を隠される
簡単にまとめると以上の内容になります。
特に、2番目のズボンを脱がされ
性器を公衆の面前で晒される事を契機に
Aは不登校となってしまいます。
一般常識で考えると犯罪になりますし、
責任能力が認められる中学生にもなれば
やった事とその結果もたらされた被害について
十分理解している事になるので、
言い逃れは出来ないでしょう。
加害生徒でよくあるパターンの通り、
今回の加害生徒達は「ほんのじゃれ合い」や
「からかい」のつもりでやっているので
犯罪でも「罪悪感」は
全くと言って良いほどありません。
加害生徒達が行ってきた行為を
裁判で争う為には、
やはり被害に遭った証拠を揃えるしか
方法が無いので、
「暴力」の内容をベースに「傷跡」や
「他の生徒からの証言」、
「壊されたもの」を重点的に
集めなければならないでしょう。
クラスでの被害者と加害者の様子

当時の状況を裁判ではどの様に
判断していたのでしょうか。
当時の「クラスの状況」を示す
書類を元に裁判で明らかになった事は、
- 加害者であるBとCはクラスの中でも「スクールカースト」が上位の生徒である
- 誰もBとCに逆らうことが出来ない
- 他のクラスメイトはAがBとCにやられていても助ける事はしなかった
となっています。
※いじめが起きているクラスに多い生徒間の階級制「スクールカースト」について詳しくまとめた記事を載せていますので一度読んでみてください。
いじめのターゲットとして
スクールカーストの下層に追いやられたAは
常に「孤立無援」の状況に
置かれていた事が判明しています。
また、誰もBとCに逆らうことが
出来ない事と関連して、
当時のAがいたクラスの状況は
「学級崩壊」になりかけていました。
なので、他の生徒も
自分がターゲットにされない様に
関わる事を避けていたのかも知れません。
先ほど書いた内容と重なるかもしれませんが
今回の様に「犯罪」として扱われる
内容の問題であれば
具体的な内容を書面などの
形に残しておく事が大事になってきます。
- 「いつ」からやられているのか
- 「何処」でやられているのか
- いじめの内容は「何」か
- 「誰」にやられたのか
- いじめの理由「何故?」
これを元に「いじめ」を形に残す事で
内容が明確になると共に
「責任」も明確になります。
今の学校で起きているいじめについて
「仲裁者」を増やそうとしても、
スクールカーストや先生の質など
様々な問題が障害になってしまい
問題の解決策にはならないかもしれません。
一番大事なのは学校と子供(保護者も含む)の
信頼関係だとは思いますが、
いじめが犯罪行為を含んでいるのであれば
早急に警察など「第三者機関」を利用して
解決に向かう方が早いと思います。
では、次に「学校の対応」はどうだったのかを
詳しく見ていきたいと思います。
裁判でも「学校の対応」が争点となり、
判決の核心となっています。
学校の対応はどうだったのか

今回のいじめ問題が発生してからの
学校の対応はどうだったのか!?
裁判では、Aが自殺をするまでの間を
「いじめ発生~夏休み前まで」と
「夏休み明け~自殺まで」の2つに分けて
「学校の対応」がどうだったのか
争われています。
いじめ発生~夏休み前までの学校の対応

今回のいじめが発生したのは
Aが中学2年生の終わり
(2月くらい)からで、
Aが自殺してしいまったのは
3年生の2学期の11月26日になります。
内容は冒頭で紹介した通りで、
ほぼ毎日の様にBとCにやられていた事が
裁判で判明しています。
問題が発覚した時の学校の対応や
様子を簡単にまとめてみると、
- Aの学年は非常に荒れていて、授業中に外に出たり騒いだりして「学級崩壊」をしてしまう恐れがあった
- 3年生に進級する時には「クラス替え」は通常行わないが、Aの学年だけ異例のクラス替えを行う
- BとCに無理矢理ズボンを下げられ性器を露出させられた事件では、別のクラスの生徒から報告を受けて後日担任の先生が事情聴取を行うが、Aからは「いじめでは無い」と報告を受けて対応はしていない
- 理科の授業で「顔にサインペンでいたずら書き」された時には、理科の先生は現場を見ていたのにも関わらず、いたずら書きしたBとCには注意をしなかった
- BとCに先生の目の前で暴力を受けても、見ていた先生は何も注意しなかった
となります。
Aの学年は非常に荒れていて
「学級崩壊」の傾向があり、
担任の先生だけではクラスの状況を
正常に保つ事が出来ないと
裁判で明らかになっていて、
Aが先生にやられた事を言わなかった理由も
言っても無駄と判断した事が判明しています。
授業中に外に出ることは、
普通に考えてあり得ないですよね。
それが日常茶飯事で、しかも通常行われない
「クラス替え」を行ったと言う事は
それだけ状況が
切迫していた事になるでしょう。
Aが実際に行われた暴力やいじめを
「口頭」でしか注意出来ない状況や、
目の前でいじめが行われているのに
何も注意しなかった事実を考慮すると、
Aがいじめに遭っていても
対処する事が出来ない、その気が無い
と判断されてもおかしくないでしょう。
※いじめを認めようとしない・対応しようとしない「学校の対応の不備」について詳しくまとめた記事を載せていますので一度読んでみてください。
以上、「いじめの発生~夏休み前まで」の
学校の対応をまとめてみました。
次にまとめるのは「夏休み明け~自殺」までの
学校の対応になります。
夏休み明けではAのいじめに進展があり、
いじめの状況が一変します。
夏休み明け~自殺までの学校の対応

この夏休み明けから
Aが自殺してしまうまでの期間は短く
大体9月くらいから11月26日までの
2ヶ月間となります。
この2ヶ月でAに一体何があったのか!?
夏休み明け後のAの様子を
裁判の内容も元に見ていきましょう。
Aは学校の休み時間中は
ずっと机にうつ伏せになり
クラスの子と接触を避ける様になります。
誰とも話をせず、家に帰る時も
一緒のクラスの生徒ではなく
他のクラスの友達と帰る様になりました。
クラスの子との接触を避け続けてきた為か
BとCからの暴力も減り、
問題は徐々に沈静化していきます。
そんな中、Aが不登校になる
キッカケの事件が起きます。
10月26日に行われた「遠足」で、
Aはその遠足で今まで沈静化していた
いじめを受けてしまいます。
クラスの子(BかCかは不明)に
リュックを奪われ坂の下に突き落とされ
持ってきた弁当も手を付けることもせず
帰ってしまいます。
そして、Aは11月から
不登校になってしまいました...。
それに伴い学校もAが11月に入ってから
不登校になった事に対する対応に
追われてしまいます。
対応をまとめると学校が終わってから
Aの家に行き、登校を促す感じの
対応になりますが、
Aは登校をする事無く
自室に籠もりっきりになります。
その後の学校の対応は、
時々Aの家まで様子を見に来たり
他のクラスの子がお見舞いに来る様になったり
いじめよりも「Aの心のケア」を重点的に
対応し始める様になりました。
その対応のおかげかAは時々訪れる友達を
部屋に招き話をしたりゲームをしたり、
少しずつ心を開いて行く様に見えました。
そして11月26日、
Aは自室で首を吊り自殺をしてしまいます。
自殺をしてしまった原因は
誰が考えてもいじめにあると思いますが、
実際にいじめが頻繁に行われていたのは
「夏休み前」で、
自殺をしてしまったのは
「夏休み後」になります。
しかもいじめが一度「落ち着いた」後に
自殺をしていますので、
「いじめ」と「自殺」の因果関係が
どの様に裁判で判断されるのでしょうか?
以上、学校の対応を
「いじめ発生~夏休み前まで」と
「夏休み明け~自殺」までの
2パターンに分けて見てきました。
大まかにまとめると、
- 「いじめ発生~夏休み前まで」ではいじめが陰湿化しており、学校の対応は酷いものばかり目立つ
- 「夏休み明け~自殺まで」では問題が落ち着いており、Aが不登校になった場合は積極的にケアに回る
となり、特に「夏休み明け」には
問題が沈静化している事が
気になる所でもあります。
問題が陰湿化している時に
Aが欠席した回数は少なく、
沈静化した後の11月頃に
不登校になっている点も
裁判ではどのように影響するのかも
気になります。
では次に「Aに起こったいじめ」に対する
裁判の内容を詳しく調べて、
裁判ではどんな事が争点となっているのかを
詳しく見ていきたいと思います。
裁判でどう判断されたのか
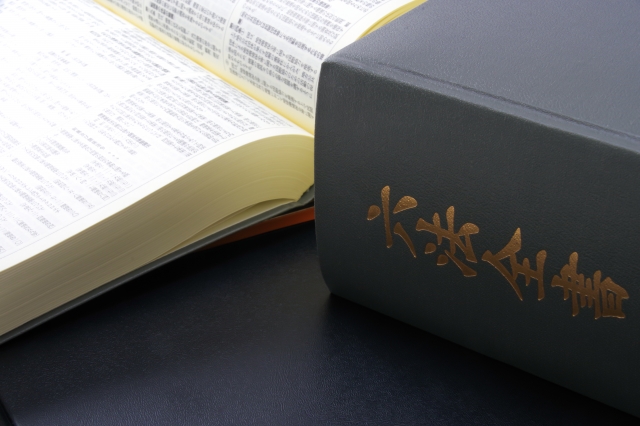
今回学校で起きたいじめ事件を
裁判ではどの様に判断したのか!?
先に遺族側が求めた請求内容をまとめ、
「いじめとうつの関係」が裁判で
どう判断されたのか
をまとめていきたいと思います。
この記事の一番のポイントになりますので
内容が少しだけ長いです。
※今回紹介している栃木県の
中学校いじめ自殺事件は「控訴審」と言って
一度裁判(原審)をして判決が出て
不服の場合に行われる裁判になります。
なので、
- 「被控訴人ら」=鹿沼市、栃木県
- 「控訴人」 =原告(A君の両親)
になります。
元々の遺族側の請求内容

今回の裁判で、もともと遺族側が求めた
請求内容(原審の請求内容)は、
被控訴人らは各自連帯して、控訴人に対し、約5400万の損害賠償金を支払う
原審で認められた請求内容は、
被告らは各自、原告らそれぞれに支払った和解金である約120万をもって損害賠償額を認める
控訴審で認められた内容は、
被控訴人らは各自連帯して、控訴人に対し、約1100万の損害賠償金を支払う
とされました。
「いじめ」と「うつ」について裁判ではどう判断されたのか

今回の問題とAが
「うつ」になってしまった事の
関連性について
ここでまとめていきたいと思います。
一番重要なポイントは
「いじめ」のせいで「うつ」になった事を
どう証明するのか、です。
今回の裁判では
「ICD-10(国際疾病分類)」に基づく事実確認
をベースにしていて、
うつ病になった経緯を明確にしています。
(うつ病エピソード)
ICD-10に基づく「うつ病エピソード」をまとめると
- 集中力や注意力の減退
- 自己評価と自信の低下
- 罪責感と無価値感
- 悲観的な考え方
- 自殺観念や自傷行為
- 睡眠障害や食欲不振
の6つが挙げられ、
Aはこの6つの項目全てに
当てはまる結果となります。
裁判で認められた理由を
番号別にまとめると...
- 3年生になってからAの集中力や注意力が激減した事を家庭教師の方が証明
- Aに起こった事実から容易に推察されるし、教師に事実を言わなかった事からも窺える
- 母親に対し「俺にもうお金かけなくても良いよ」とポツリとつぶやく
- 「1、3、」の内容を考慮すれば容易に想像が付く
- 自殺の方法が「首つり」という致死性の高い方法をとっている事
- 不登校になってから部屋に籠もりきりで食事を出しても廊下に置きっ放しで手つかず
そして、この結果が元となり
少なくとも不登校の時点で
Aはうつに掛かっている事が
裁判で認められる事になります。
第三者の証言を取れていることが
認められる大きな要因だったのでは
ないかと思います。
(家庭教師の方)
より確実な方法を言えば
病院の診断書なども良い方法だと
思いますが、
今回の裁判(控訴審)では
診断書の内容は触れられていません。
※「診断書」について詳しくまとめた記事を載せていますので一度読んでみてください
「うつ」と「自殺」との関連性は??

先ほど、少なくとも不登校の時点で
Aはうつに掛かっている事と
「いじめ」と「うつ」の関連性は
裁判で認められました。
では、「うつ」と「自殺」との関連性は
どうだったのでしょうか??
結果から言うと、
- 「うつ」と「自殺」の因果関係を認めない
- 1学期終了時でAがうつ病に掛かっているとは認められない
と判断されています。
今回の事件で「うつ」になった事は
認めているけど、
正確な時期を確定できる証拠が
集まっていないという事が
「うつ」と「自殺」が認められなかった
要因として考えられるでしょう。
前述した「学校の対応はどうだったのか」で
まとめてる通り、
3年生の1学期に起こった事実に対する
「安全配慮義務」については
責任を認める一方、
「夏休み明け~自殺」までの内容については
認めないとしました。
問題があってから「夏休み」を挟み
2学期からは沈静化している事が
ネックになっている様で
2学期からの学校の対応については
学校の責任は認めないとしています。
しかも、夏休みは学校生活の中で
一番長い休みになりますから
休み中にその他の原因が
あったのかも知れないと言えると
いう事になるのかも知れません。
判決でも次のように述べています。
Aに対するいじめは,暴行自体は深刻な傷害を負わせる程度であったとは認めることができず,いじめにより受けていた精神的な苦痛が他者からは把握し難い性質のものであったことを併せ考えると,Aが1学期中に受けたいじめを原因としてうつ病にり患し,自死に至るのが通常起こるべきことであるとはいい難く,いじめを苦にした生徒の自殺が平成11年以前にも度々報道されており,いじめが児童生徒の心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし,自殺等を招来する恐れがあることなどを指摘して注意を促す旧文部省初等中等教育局長通知等が教育機関に対して繰り返し発せられていたことを勘案しても,甲中学校教員らが,第3学年1学期当時,Aがいじめを誘因としてうつ病にり患することを予見し得たとまでは認めるに足りないといわざるを得ない。
と、この時期に確実に「うつ」に掛かったと
証明するものが無い事が理由として
述べられています。
以上、裁判での内容をまとめると、
- 「いじめ」についての「安全配慮義務違反」は認める(いじめ発生~夏休み前まで)
- 「うつ」になったのは少なくとも不登校の時点から認められる
- 「うつ」に掛かった時期は、いじめが深刻化した1学期ではない
- 「安全配慮義務違反」と「うつ」「自殺」との因果関係は認めない
となります。
ここからは個人的な意見になりますが、
いじめと安全配慮義務違反は認められたので
後は「うつ」になった確定的な時期を
証明する事が出来れば
違った結果になったのかも知れません。
それを証明する事は容易ではありませんし
精神的な損害は外部からは分かりにくい
性質を持っていますので
「目に見える方法」で証明する事が必須
になると思います。
【いじめ裁判】「うつ」になった事を裁判で認めさせるには まとめ

今回は「いじめ 裁判」をキーワードに
平成11年に起きた栃木県中学校の
いじめ自殺事件の判例を紹介しました。
判例を元に、
- いじめの内容
- 学校の対応
- 裁判でどう判断されたか
に分けて詳しく紹介しています。
そこから、今回の裁判の争点である
「安全配慮義務違反」と「うつ」や
「自殺」との因果関係についてまとめ、
- 『いじめのせいで「うつ」になった事を相手側に認めさせる』事は出来るのか!?
- また、「認めさせる」為には何が必要なのか
を中心にまとめた記事になっています。
さらに個人的な意見かもしれませんが
「いじめ」と「うつ」の因果関係について
どのように証明していけば良いのかを
まとめてみると...
- もし「うつ」になったのであればその事実を形に残す(診断書など)
- 「うつ」になった場合「いつ」からなのか形に残す(診断書やうつになった経緯など)
- 出来るなら、第三者の証言もあわせて欲しい
- 時期に開き(今回の夏休みを挟む場合)があると事実確認する事が難しくなる場合があるので対応を早める
という事が考えられます。
今回の判例が制定された時には、
まだ「いじめ防止対策推進法」が
制定されていないので
この事実は違った結果になったかも
知れませんが、
今書いた4つの内容は
重要なポイントになるでしょう。
さらに「いじめ=自殺」に繋がる
可能性が高いので、
早めに第三者機関(弁護士や行政書士)に
相談して対策を練ることも欠かせません。
最後に「いじめ-ラボ」では
「我が子のいじめ」をテーマに
記事を更新していますので、
他の記事も良かったら読んでみてくださいね!
いじめの対処法 「分からない」「どうすれば」をメールで受付中!

この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。
さらにこの記事を読んでいる
あなたをはじめ、
今現在いじめで悩んでいる方々に
少しでもお役に立てれる様に
日々勉強をしています。
そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、
分からない事などについて、
私たち家族が経験した事を中心に
『「いじめ-ラボ」の相談コーナー』で
随時相談を受け付けております。
- 我が子にいじめが発覚して、これからどうして良いのか分からない
- 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...
- 子供の様子がいつもとおかしい
- 誰にも相談出来なくて、今の気持ちを聞いて欲しい!
など、具体的な内容について
相談を受け付けていますので、
私たち家族の経験が
少しでもお役に立てたら嬉しいです。
※「いじめ問題」について具体的な質問やお問い合わせを受付中!
長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。


コメント